ガラス乾板(臭化銀ゼラチン乾板)が1871年(明治4年)にイギリスで発明されると、1874年には市販が始まり、撮影前に感光材を作る手間が省け、出来合いのガラス乾板を買ってきて撮影することができるようになったため、アマチュアの写真家たちも写真撮影に入り込むようになります。ただしガラス乾板(臭化銀ゼラチン乾板)がプロ写真家の間で主流になるには、1879-1880年ごろまで待たなければならなかった
日本では、ガラス乾板が普及するのにはさらに時間がかかり、明治10年(1877年)ごろは、まだ主流はガラス湿板(しつばん)だったので、上野 彦馬(1838年10月15日(天保9年8月27日) – 1904年(明治37年)5月22日)は、
明治10年の西南戦争では、日本初の戦場カメラマンを、ガラス湿板(しつばん)で行うという苦行を実施
ガラス湿板(しつばん)は、完成して5分くらいで撮影しないと、感光材が乾いて使えなくなるので、現地で撮影前にガラスに感光剤を塗り、5分以内に撮影するという、とんでもなく手間がかかる代物でした
「古写真に見る西南戦争の記録-「彦馬が見た西南戦争」」
開催期間:2010年8月3日(火)〜2010年8月29日(日
日本カメラ博物館
https://www.jcii-cameramuseum.jp/photosalon/2010/08/03/9117/
の記事によれば、
薩摩の反乱軍鎮圧の、明治政府征討参軍(司令官)川村純義の命により、戦場の様子を撮影することを命じられ、
当時使われていた湿板写真は、その場でガラス板に感光材の塗布をし、現像処理までを行わなければなりませんでした。そのため、彦馬はこの撮影用に特製の携帯暗室までしつらえ、撮影助手の弟子二人と機材を運ぶ人夫8人を含む、総勢11名の撮影隊を結成して撮影に挑みました。まだ危険が残る戦場での撮影に、彦馬らは多大な労力を費やしたようです。(上記日本カメラ博物館)
と、とんでもない規模のスタッフを引き連れての撮影だったそうです
まあ、そういう中で日本の写真は発展していきますが、欧州では、写真を芸術ととらえ、美術館などが写真を購入したり、写真家にスタジオ提供するなどの、創作の道具としての写真が1860年代にはもう起こっていましたが(写真の発明後、長く敵視されていた、ボケやブレ、ソフトフォーカスを使った表現【美術の歴史とボケの歴史】クラインに先駆け、ボケ、ブレを写真表現に取り入れたプロ写真家たち)、
コダックが、持ち運びが簡単な、フィルム式カメラを1885年に発売、1912年からは折り畳みができてポケットに入るカメラを発売し、しかもコダックの現像工場に送り返せば、フィルム現像、プリント、フィルムの再装填までしてくれるサービスも開始、コダックは1900年前後に各国に拠点工場などを建設(実際は写真の普及時から今も続く、写真とピクトリアリズム(絵画主義)pictorialism, pictorialisme: 誤解がはびこる絵画主義 ピクトリアリズム自体が長い流れの通過点であることを誤解・忘れさせるような記述が特に日本で多すぎ:写真と絵画の相互影響)
アマチュアにとって、写真の参入障壁がだいぶ減りました。まあ比較的高価であったのは確かなので、ある程度小金持ちでないと写真趣味はできませんでしたが
カメラの一般人への普及とともに
各種カメラ写真指南書や雑誌が日本でも多く出始めます
「写真人とその本 3 /高桑勝雄」
日本カメラ博物館 JCII ライブラリー
学芸員 宮﨑真二
クリックしてphotographer_books03.pdfにアクセス
三宅克己『写真のうつし方』(阿蘭陀書房・1916 年)は、その後アルスと出版社が名前を変えてから増補版で売られるなど、大ヒットとなり
1921年に創刊された『カメラ』(CAMERA)という雑誌は、月間コンテストで読者の写真のコンクールを開始、また、学校にいかずとも現像やプリント技法なども身につくような記事も多く書かれた
また、これら小型カメラ(F11でシャッタースピードは1/20くらい、固定焦点)、アマチュアが撮影すると、必然的にピンボケ、ブレが多い写真が出来上がる事情もあり、これが以前の時代より、ブレやボケに寛容な余地が増えるきっかけになったと邪推する人もいます
以下の東京都写真美術館の刊行物には
「日本の芸術写真──写真史における位置をめぐって」
特別講演録(2011年4月16日)東京都写真美術館
https://topmuseum.jp/contents/images/info/journal/kiyou_11/03.pdf
日本では、写真を美術として認知する文化は、少なくともプロ写真家としてはあり得なかった日本独自の文化があったことを光田という人が紹介
いま、写真はアートフェアでも盛んに売買されて、アートマーケットのなかに入っています。つまり写真を美術作品として購入する人がいるということです。こういう傾向はここ20〜30年ぐらいのことじゃないかと思います。つまりここに「芸術写真」と言われて展示されている作品は、すべて売買の対象にほとんどなっていなかった。写真をつくって販売することを職業とするアーティストはいなかった。ですから、芸術写真をつくっている人はアマチュアと呼ばれていて、やりたいからやっていたんですね。(東京都写真美術館上掲 19-20)
まあ、東京写真博物館の特別講演録には、資生堂初代社長・福原信三が冩眞藝術社を創立し『冩眞藝術』という機関雑誌で、「釣り」というピンボケみたいな写真を公開など、
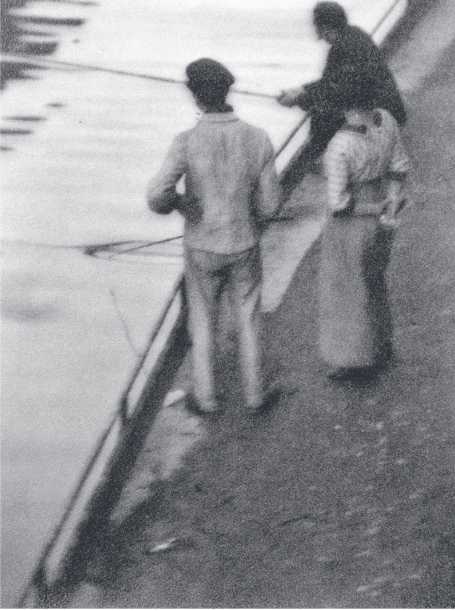
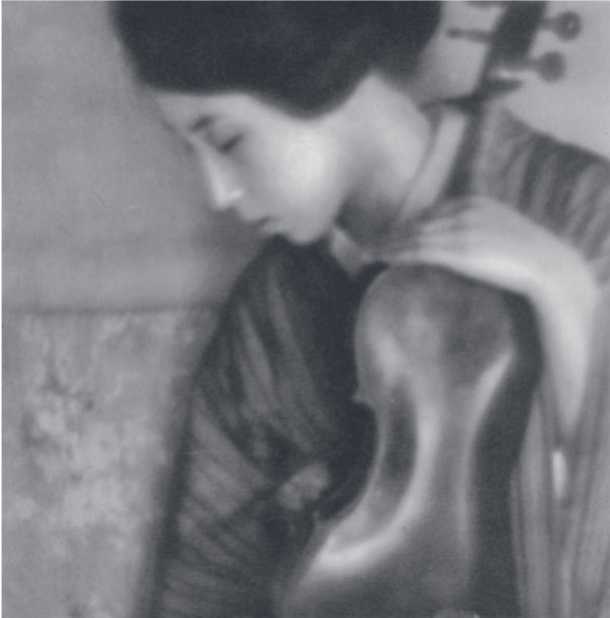
アマチュアだからこそピントの合っていない写真に創作性を見出すという流れがあった時期もあるようです
というのも当時は、芸術写真はアマチュアの表現で、それを職業として認知する文化は日本ではなかったからだと
とはいっても、写真集という形の本で、作品写真を公表する人はいましたが、一つ一つの写真を絵画のように作品として扱って売買する文化が日本にはまだなく、写真家にとって作品写真という概念は、ご飯を食べる手段としては成立しきれていなかったということでしょう
現在日本では、19世紀末から20世紀初頭に起きたピクトリアリズム(絵画主義)を、狭い範囲の運動としてとらえて、ソフトフォーカス(あるいはソフトな印画法)が特徴的な作風のように読めてしまうように紹介することが、三文学者含めて多くありますが、実際は1840年代にはもう起きていた、写真というものは絞って隅々までシャープな記録性を追求するものであるという、記録主義と対抗する、ボケ、ブレ、アレなど欠点とされるものを、創作手段としての写真の在り方を追求する流れの線上に、ピクトリアリズムもあるので、ボケが出やすい絵画的な構図も、絵画の肖像画にヒントを得て始めたもので、保守派の写真協会はお冠だった、絵画主義=ピクトリアリズムの一種なんです。
実際、一部の本では19世紀末ごろから起き、1920年代まで続いたとされる、ピクトリアリズム(絵画主義)の、最初の発端となったとされる、英国のピーター・ヘンリー・エマーソン(Peter Henry Emerson (13 May 1856 – 12 May 1936))は、ソフトフォーカスや、解像感のない写真自体は、好みではなく=一応試したがw、シャープでピントの深い写真が好みであったものの、シャープを追求していて逆に嘘くさい風景写真となっている。写真は技術的記録手段ではなく、芸術創作の手段でもあると、訴え続けていました。(写真におけるボケ、ブレ、アレなど、不完全性を表現に取り入れる作風の歴史)
このため、彼が追及した写真は、Naturalism(自然主義)であり、ピクトリアリズム(Pictorialism絵画主義)ではないという分類もできるともいえます(実際そう分類してる人も)が、ピントを合う角度を変え、いらないものをぼかし、主題を目立たせるための、ティルトあおり(Selective focus=ピントを絞るのが普通だった大判や中判カメラでは、よく使われたボケコントロール)などの利用など、従来の隅々までシャープでピントも深く、に反する絵画主義の影響もみられ、広義ではピクトリアリズムの一種であるとも言えます
彼が1889年に出版したNaturalistic Photography for Students of the Art(現在は、著作権切れなので、https://www.gutenberg.org/ebooks/56833などで無料で読める)では、自然を忠実に再現する表現力は写真が最も豊かであるとし、写真における風景撮影は、極力その光景を改変しないことが大事であると諭しました。*とはいっても、特にダゲレオ式(銀板)撮影のような極端にエッジが立つような風景画も、彼は一方で嫌悪したので、ソフトフォーカス的な要素も入れてみようとしたが、それも彼の好みに合わなかった経緯がある
てなわけで、19世紀末ごろから、1920年代後半くらいまでの時期で、どんな作風がピクトリアリズム(絵画主義)という話はないです。フランスでは運動のリーダー格が、ソフトフォーカスレンズを開発販売するなど、それまでより、表現の幅が広がる技術開発をしていたのは確かですが。また1920年代にはようやく一番保守的なフランスでも、ボケやブレを生かしたことを、大きく売りにした写真館が多数建てられるところまで変化があったので、一部特権グループの運動は必然性がなくなったのです。*この時代のピクトリアリズムは、特に日本ではソフトな描写が~とレッテル張ったほうがわかりやすくて、もうかりやすい評論家や学者という人種の事情はあるかもw
上で紹介した高山らのアマチュアグループは、欧米の情報を入れてソフトフォーカスを積極的に取り上げましたが、その後はソフトフォーカス的な作風は減っていくので、絵画主義=ピクトリアリズムから離れたと一部で書かれていますが、
記録主義者に近い作風が後半になると増えます。と言っても、そこには絵画からの影響の作風もまだあります(本人がそこまで意識してやっていたかは不明)
*日本は1970年末まで旧著作権法が有効で、写真の著作権は、製作後あるいは公表後13年(それ以前は10年)と、写真に関する著作権は大幅に制限され、短かったので、資産価値が生じにくかったのも、写真を美術表現として用いるのが、日本でなかなかはやらなかった理由かもしれません。(映画についてもニュースなどは、著作権性が低いとされ、公表後10ー13年で著作権は消滅した。著作権性のあるとされた映画は、著作権は38年ありました)2023年現在では、小説などは、ペンネームなど変名を使って公表した場合、公表後70年著作権があるとされますが、写真はペンネームを使っても、死後70年間保護されると、写真の著作権は大幅にアップ。
**写真が発明実用されたとき、Flouというフランス語の単語(英語ではBlur)が、ボケやピンボケ、ソフトフォーカス、あるいはレンズの解像度不足など、シャープでない部分の表現を指す言葉として使われて、今日のようなBokeh(ボケ)という、ピントが合っていない部分の描写を特に意味する単語はなかった、英語ではBlurredやOut Of Focusが今のボケと同じ意味
***ただし、海外では、写真は絵画や彫刻、版画などと同じような、芸術表現の一種であるという考えは、1840年代から、ロマン主義画家ウジェーヌ・ドラクロワ(《民衆を率いる自由の女神》1830年で有名)などの画家、あるいは画家出身の写真家たちなどによって始まっていて、職業写真家協会がそうした意見に激しい敵意を見せるなか、画家などの、写真以外の美術家たちが、ボケやソフトフォーカスなどを前面に出す写真家を金賞に選んだり、作品を購入など支援するのも普通でした。
英国のDavid Wilkie Wynfield (British, 1837-1887)は、写真と画家の二足の草鞋を履きましたが、
絵画では、以下のように背景をぼけたように描く手法で、目立たせたいものに目線を誘導する表現は19世紀には当然であったので(**新古典主義という当時フランスでは特に強かった絵画手法では、ボケを強く出す手法は、まだ一般的ではなく、極力ボケを抑え気味の、パンフォーカス的な描写が強かった。19世紀中ごろからの印象派は、写真でいうブレや、アレに通じる表現が特徴だが、ボケに関しては、パンフォーカス的な描写が多く、ボケ否定とみられる作品が多い)、


彼は、写真でも、主役以外や顔以外をぼかしたり、画像自体をぶらすことも普通でした。David Wilkie Wynfield の写真家としての作品 1860年ごろ

こうして、多くが写真以外の専門がある美術家たち(と少数の写真専業プロ)は、写真を撮影するときは、ボケ、ブレ、アレを効果的な表現手法として用いる一方、写真家専業の多くは、隅々までシャープなパンフォーカスを志向し、ボケ、ブレを間違いとする立場をとり、写真専門の集まりや機関雑誌では、ボケ、ブレ批判が多く出ます
写真を依頼する人たちですら、肖像写真家たちは隅々までシャープなポートレートを撮影するのを喜んでる不思議な連中だと、1865年にフランスの詩人が母親に書き送ったりしているのは、写真の発明後、長く敵視されていた、ボケやブレ、ソフトフォーカスを使った表現【美術の歴史とボケの歴史】クラインに先駆け、ボケ、ブレを写真表現に取り入れたプロ写真家たち でも紹介
そして、1890年ごろのピクトリアリズム(絵画主義)として、ボケ、ブレを欠陥とするまだ多数派の写真家たちに対抗する、比較的大きな流れも生じるようになっていきます
1910年代末期からは、可能な限り、ボケを生かす肖像ポートレートを撮影する写真館がフランスなどで多数登場し始めます Gaston & Lucien MANUEL(Manuel兄弟)Henri Martinieとかがその中の代表とされます 目と鼻と口以外はぼかす、ポートレート撮影手法でした。それまでは、正当ではないと、異端視されていたボケ、ソフトフォーカスが、大手を振って写真表現の在り方として認められるようになったのです。
こんな感じ



日本の1920-1930年代のアマチュア写真家たちが、英国では1850年代ごろからマイナーで批判者が多数だが、認知はされていた、そしてようやく1910年代後半には、フランスでも、特に人物撮影では認められてきた、ボケやソフトフォーカス写真に影響されていたのは確かでしょう
*ほかのジャンルでは、その後もボケやブレは邪道とする声が圧倒的な時代は海外でも続くし、日本ではこうした創作風の写真は、アマチュアのするものという時代が長かった=日本ではプロの写真家は記録性を重視するのが本道で、絵画のような創作の手段での作品としての写真が認知されるのは1980年代ごろから
芸術写真の精華 日本のピクトリアリズム 珠玉の名品展
東京写真博物館
https://www.topmuseum.jp/contents/exhibition/index-350.html
1920年ごろは、ピグメント印画法という、のちの銀塩プリントとは異なる方法で、銀を使わず印画紙を作り、その方法で作られたプリントは、いわゆる銀塩プリントより柔らかい表現ができることで、まあ、そういった効果をソフトフォーカス風などに応用する流れがしばらくあったということですね
また、写真を大きくトリミングして、粒子の荒い、ピントのぼやけた写真プリントを作ることも、この時代のアマチュア写真家は行っていました
この時期は、レンズ特有のボケについての議論は、日本でまだ盛んではなかった
日本の風景写真家・白川義員(1935年 – 2022年)は、山岳写真の技法 (1973年)という本の中で、風景写真において、主題を引き立たせるために余計なものをぼかすのは邪道で、ピントは隅々まできっちり合うようにパンフォーカスすべきで、構図で邪魔なものは構図の外に外してしまうのが正しいという、写真が発明されたときにできた、職業写真家たちの鉄則を風景写真では説いていました
いまでも風景写真は隅々までピントが合っていることが望まれる、絵画で許されるボケなどの表現手法は写真では許されない、という主張は、こうした人たちに影響を受けた世代には根強い
風景写真は隅々までシャープなのが好ましい?【写真にまつわるニセ科学と怪談に注意】
まあ、水の流れを表現、あるいは海面や湖面をなだらかにする、雲をぶらして、よりインパクトのある空を表現するためにスローシャッターを使って、水や雲をぶらす手法は、現在では風景写真でも多用されてます
(現在でも服が主役のファッションポートレートや、ビジネスポートレートは服や手にもピントが来るように絞るのが基本ですが、その中に、ボケを生かした写真を混ぜることはタブーではなくなっています)
プロの写真家たちだけが美術理論をかたくなに否定する流れは今でもあります。
日本では、森山大道が1968年に、ボケ、アレ、ブレを前面に出した写真集を公表し、ようやく大きなメディアでもボケやブレを、写真表現に生かす手法が、プロの写真家によって堂々出されることとなります(**森山大道は、当時刊行されていたカメラ毎日という雑誌に持ち込みを仕掛けていて、カメラ毎日 1967年1月号 新年号には、写真におけるブレとボケと題する特集が組まれ、森山大道の写真が、「にっぽん劇場」として公開されており、その反響で書籍化となった)
中平卓馬1938年 – 2015年9月1日も、この時期森山大道らと組んで同じような作風を出しますが、
同人雑誌として多木浩二と中平が組み、高梨豊、と詩人の高梨が『プロヴォーク』を1968年11月に始め、二号から森山大道も参加
中平は、数年後には、その作風が商業写真にも使われだし通俗化したとして、そうした作風を否定しだします。
中平が、ボケやブレを肯定的に取り入れたのは、
『「写真はピンボケであったり、ブレていたりしてはいけないという定説があるが、ぼくには信じがたい。第一、人間の目ですら物の像をとらえる時、個々の物、個々の像はブレたりピンボケだったりしているのだ。それをイマジネーションが統一し、堅固な像に固定している、ということではないか』(鳥原2016から引用)
と、その動機を書いているのですが、彼は19世紀の欧州の美術家たちと同じような「写真家たちの崇拝する写真のおかしさ」のことを言いながら、ブレやボケに対する態度は、特に人間に心地に良い視覚効果と人間の感情(人間の内面)や、その場の雰囲気の表現を考えて、ボケブレを生かす美術家たちから派生した、19世紀末から20世紀初期のピクトリアリズム(絵画主義)Surrialismなどを経由した一環とした流れと、本質は異なるところに、中平は写真の意義を感じていた可能性があります
まあ、アサヒカメラ1969年4月号で中平などの対談特集が組まれ
『言葉と写真表現の関係だった。新倉は写真が言葉をトレースすれば「写真とは別のものになってしまう」として否定し、中平は言葉から逸脱したものだけを視覚化するのだと発言している。つまり「写真はことばのための資料」であり、「真実のことばを一つ作るために、写真を資料としてどんどん提出していく」という立場をとる。そして来るべき言葉を待つのだと述べている。』(鳥原2016年から引用)
と、中平は、言葉の意味を表現するために写真がある、言葉に正当性を与える証拠資料としての記録写真が、写真の本来であるとし、「記録としての写真が、写真のあるべき姿である」という、結局は19世紀から、画家や美術家が表現の手法として、写真もボケやブレを生かすべきであるという流れで来た、ボケ、ブレ写真の普及努力とは、離れたところに、中平はいた。記録性が高いことが求められる報道写真にちかい
さて、これまではアマチュア写真同好会の会報に載るくらいだった、ボケ、アレ表現に、森山らで、当時のカメラ雑誌がその作風で埋め尽くされるまでになります。一気に影響されたのが国鉄のポスター写真、少なからずの、ブレを生かした表現の写真がこの時期から採用されます
B1ポスター 国鉄 「神々のふるさと 出雲大社」 1974年 Discover Japan/ディスカバー・ジャパン 島根県 駅 構内 掲示物 JR 昭和49年
https://aucfree.com/items/l640030038
(オークションでの販売のための、一定画素数以下の見本写真としての複製は、著作権法の例外的扱いで認められている)
彼は、こうしたボケやブレの表現の商業写真への浸透により、逆に写真が冒涜されたと感じるようになった。
中平卓馬は、写真同人誌「プロヴォーク」などで、森山大道と同じように、ボケ、ブレ、アレ写真を同時に展開しましたが、直後に写真は記録でなければならないという、人間の感情などを表現する手法で写真を撮影するのは邪道であると、写真が普及し始めた1840年代からの、特にフランスの写真家たちと同じような考えを公表していました。「リアリティ復権」『デザイン』(一九六九年一月号)と題する彼の著述
ボケ、ブレ、アレを表現に使った写真を多数公表した時期に、同時にそう言った写真は本来は邪道であるとも書いていた、中平卓馬は、ボケ、アレ、ブレ表現を、国家や商業資本権威や、ライバル写真家などへの当てつけで行っていただけで、本心では絵画のような表現としての写真の存在が許せなかったという話があります。
また、中平のボケ、アレ、ブレ否定は、妙に政治色が強い
「記録という幻影」『なぜ、植物図鑑かー中平卓馬映像論集』1973
という本の一章で、写真は記録であることが第一の物質的な前提であると信じられ、主張され、人はそれに疑念を持ったりはしない、と自分が数年前にやったことを否定する文章がでます
国鉄が当時行った宣伝ポスターのように、ボケやブレを多用することは、その光景にある不都合(肥溜め 住む人々貧困)なものを覆い隠すという隠蔽であり、写真の本来の姿であるべき「記録」から、人々から、現実にあるものから目をそらさせる手段と、中平卓馬は自分の初期のボケ、ブレをその直後に否定して回ります
1969年の沖縄ゼネスト警察官殺害事件では、沖縄の青年が、警官を殺害したという罪で起訴されましたが、読売新聞はその現場のスクープ写真を意図的にトリミングして、沖縄のその青年が犯人であったかのように世論誘導していた事件(中平は支援活動に沖縄に行って、暇なときは沖縄の写真を撮り歩いた)から、写真はその場の真実を記録するのが本来であり、こうした撮影者などの意図が介在することで、本質をゆがめてしまうような表現手法は間違っているというようになります。
こうした中、中平は非常に抽象的な、彼に敵対するものを風景としてみていく、「風景論」と、のちに、大学での美術史ごっこ評論家ごっこで金を稼ぐ人たちから称せられる、当時の映画監督なども追求した、中身はあいまいな「目に見える風景は国家権力=敵」のような、政治性の強い方向性に走っていきます。
中平拓馬のボケ、アレ、ブレ否定の過程を見れば、当時の海外からの情報的制約から、1840年代から始まり、1860年代のJulia Margaret Cameronにおけるように、写真家たちからは敵視され、ほかの芸術家たちからは絶賛されたボケ、ブレの表現や、複雑な肯定派、否定派の理屈、ブレッソンがブレやボケをピクトリアリズムや超現実主義者たちとの交流で導入した文化的な背景は、理解せず(というか今でも日本の美術史家とか写真史やってる連中もわかっているような書き方はしていない)、写真家なので海外の写真のみから学び取ろうとしていた中で、ブレ、ボケをみて、視覚的のみな面から注目しただけと思われ、のちにボケ、ブレを否定するときも、西洋で行われていた否定派の見解ではなく、抽象的なしかも政治色の強い「風景論」に走ってしまいます.
ボケ、ブレ、アレの否定が、政治色の強い「風景論」に行き着いたあたりは、中平卓馬のボケ、ブレ、アレを始めた発端は、英国やフランスにおけるもの(写真も絵画と同じく表現の手段であるべき、写真は撮影者の主観が入らない、可能な限り精密シャープを追求するのが本道)とは、そもそもだいぶ異なった動機であったともいえます。
そもそも1967年あたりから1970年代中ごろまで、日本でボケブレアレ写真が大ブームになったのは、当時は学生運動などで日本はせわしく、混乱の時代であったため、そうした政治などの状況が、かかわっていたからだという人が、現在も主流派です。まあ、三文学者と評論家の言う分析は、後付け解釈なので、本当のところはわからないが、欧米のように美術絵画の手法を否定する写真家たちへのほかの美術家たちの抵抗という流れとは、別の動機で、日本でボケ、アレ、ブレが一気に写真の在り方として認められたということはあるいは言えるかもしれない
中平卓馬は、ウォーカー・エヴァンス(Walker Evans, 1903年11月3日 – 1975年4月10日)のような、記録性を最重視したストリートフォトの方向性に進みます
ただ、中平と森山が特にボケとブレ表現で、影響を受けたクラインは、ストリートフォトでボケとブレを多用しますが、人間はボケもぶれも見える、写真からそれらボケブレを排除した非現実な世界を、「忠実な記録」というのは実際は、非論理的だとしゃべっているんですがw
日本の1960年代末期の突如として、日本ではそれまでアマチュア写真家の余興としてとらえられてきた、ボケブレ荒れソフトフォーカスを、売り込んでやろとたくらんだのは、当時は雑誌が、まだ世論などへの影響力もそれなりにあった時代で
カメラ毎日 の編集者 山岸章二 でした
彼は新人の発掘(当時はそれなりの部数があったので、取り上げられることでプロカメラマンへの道が開けた)を行う傍ら、新しい表現の可能性を追求していた
そんな中、森山大道が、ボケブレアレを引っ提げて、カメラ毎日に売り込みに来たので、山岸は一気にこの作風をはやらせようとして、短期間の大ブームを生み出すことに成功します。
しかし、読者の中には、こうした作風を全く理解せず、批判も多かったことから、山岸は、直後から、コンポラ写真と呼ばれる、米国で一部の写真家たちが始めた、パンフォーカスでブレない写真をはやらせようとしました。森山と、ボケブレを大々的に売り出した、中平卓馬は2年もしないうちに、正反対の作風のコンポラ写真称賛を始めるありさま。
というわけで、日本でのボケブレアレ旋風は短期間で終わったというのも、欧米のように、絵画表現を写真に持ってきて、それを表現として認めさせるという、基本の文化地盤が乏しい中、いきなりボケ、ブレをはやらせようとして過激な表現に走り、読者の反発も多かったので、仕掛けた山岸章二が、カメラ毎日からの読者離れを防ぎたく、正反対のコンポラ写真をはやらせたいので終わりにしたとも、言えなくもないかも。
そう、カメラ雑誌の編集者が、当時はカメラ雑誌の影響力が強かったので、ボケブレを森山などを使って、はやらせようとしたが、過剰な表現に否定派が多くなったため、中止した、雑誌によって盛り上げられたブームで、作者たちの自主性は乏しかったともいえるでしょう 中平は直後にボケブレ否定、森山大道も、数年すると、大スランプにしばらくはいるのは、山岸に踊らされた反動が出たのかも?
写真家たちの自発的な表現確立ではなく、雑誌編集者に踊らされ、雑誌のトップダウンで仕掛けられた部分もあったのが、この時期のボケブレアレが、芸術写真では、瞬間的なブームにしかならなかった理由かも
森山と中平の初期の作例(右上・右下が中平 左上・左下が森山)
当人たちの撮影の状況は知る由もないが、中平のほうが無理して「アレ」を使ってやるんだといきごんでいたような感じ
「風景論」と呼ばれる1970年代ごろの動きは、実際は、作者たちが、自分の仮想敵(商業主義、国家権力など)を「風景」として呼んだことから、「風景論」とも称されるという、「風景論」は後からできた評論家用語
アーティストトーク
〈風景〉について
静岡県長泉町IZU PHOTO MUSEUMにて開催されたトークより、2013年1月30日
畠山直哉
he San Francisco Museum of Modern Art. (畠山直哉「アーティストトーク〈風景〉について」『日本の写真にフォーカス』2022年 2月、サンフランシスコ近代美術館、https://www.sfmoma.org/essay/アーティストトーク〈風景〉について/)
森山大道も、アメリカなどの20世紀中ごろのクラインとかいった写真家の作品を学習材料にしていて、ほとんど写真からの印象が参考になっていたともいわれます。欧州などのように、長い時間をかけて、美術絵画では、ボケとブレの表現が人間の視覚的認知などを踏まえて開発されてきて、手法として確立したため、その美術製法知識があった、19世紀中ごろの欧州の画家兼業の写真家などらの、記録原理主義写真家らとの対決活動の歴史の文化は、ほとんど知らなかったとも思いますが、海外からの情報伝達が不十分な時代に生きた、中平は、ボケやブレを表現に使う欧米の写真の流れの源流を知らないまま、ボケ、ブレ写真に手を伸ばしたものの、国鉄などの商業写真に悪用されたと感じるようになり、結局は写真は本来記録手段でしかないという、意味不明の原則論に戻っていくわけです
(こう書くのも、日本の写真史とかの三文学者とか評論家とかいう、クリエーターに寄生してるごみ産業の研究とか見ても、そもそもピクトリアリズムやSurrialismが写真でどう起きてきたのか、日本の三文学者は、19世紀にはじまった神学論争を、理解していないまま、思想論としての、風景論だ、森山大道とか書いてるので、森山や中平も少なくとも1960年代にはそんな感じだったと思われます)
***報道写真は記録であるべきなのは、19世紀から現在も変わりがない
***風景写真は、ボケ、アレ、ブレを、余興的文化とみる形は、過去のような教条主義ではなくとも、21世紀も続き、21世紀になってデジタル写真が支配的になり、加工レタッチが普通の人でも簡単にできることから、過剰レタッチの是非についての議論も、JPEGかRAWのバカ議論と同じように長々続いています
[連載]アサヒカメラの90年 第11回
1969年の「わからない写真」
アサヒカメラの90年
鳥原学
2016/10/20/ 00:00
https://dot.asahi.com/articles/-/25102?page=1
https://dot.asahi.com/articles/-/25102?page=2
日本では、写真の著作権は公表あるいは創作後10-13年としていた旧著作権のからみで、1931年1月1日より前に撮影、あるいは公表された写真は、著作権が消滅(ただし日本と交戦していた連合国は戦時と占領時期約10年が加算される。ただしこれはサンフランシスコ平和条約の取り決めによるものなので、別個の平和条約を作った中国、そして現在もソ連の後継国家として、活動するロシアも、いまだ日本との平和条約が作られていないので、日本の著作権延長規定はロシアと中国のものにはありません。まあロシアとの平和条約が仮に将来できて、ロシア側が日本に著作権復活と延長の条項を認めさせることもあり得ますが、それはその時に話なので)
昭和二十七年法律第三百二号
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000302
著作物等の保護期間の延長に関するQ&A
文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html
感性の赴くままに写真を撮影することも、あるいは正解の場合もある:ウィリアム・クラインWilliam Klein ブレ・ボケ・アレを写真表現として確立したアメリカの写真家
風景写真、長時間露光=スローシャッターは積極的に使う:月夜の海岸での撮影をイギリスの写真家がYoutubeで解説
Youtubeを見て写真上達:英国のトッププロが風景写真5つの間違いを指摘【学習動画】写真がすぐ上手くなるという囁きに惑わされないように
スローシンクロ(低速シャッターと発光時間の短いストロボの同時利用)で、水上ボートなどの動きのダイナミックな動きを表現【Youtubeで学べる撮影テクニック】ブレを表現に活かす
写真におけるボケ、ブレ、アレなど、不完全性を表現に取り入れる作風の歴史
画家・エドガー・ドガEdgar Degas(1834年7月19日 – 1917年9月27日)と写真活動【印象派の画家と写真におけるボケ、ブレ、アレの歴史】
日本と欧米の写真写真のボケ文化:欧米は、初期から絵画風の写真を撮る手段の一つとして「ボケ」があり、日本はレンズを売るための手段としてのボケ描写のこだわりを広めた【写真にまつわる怖いカルト神話とボケ】